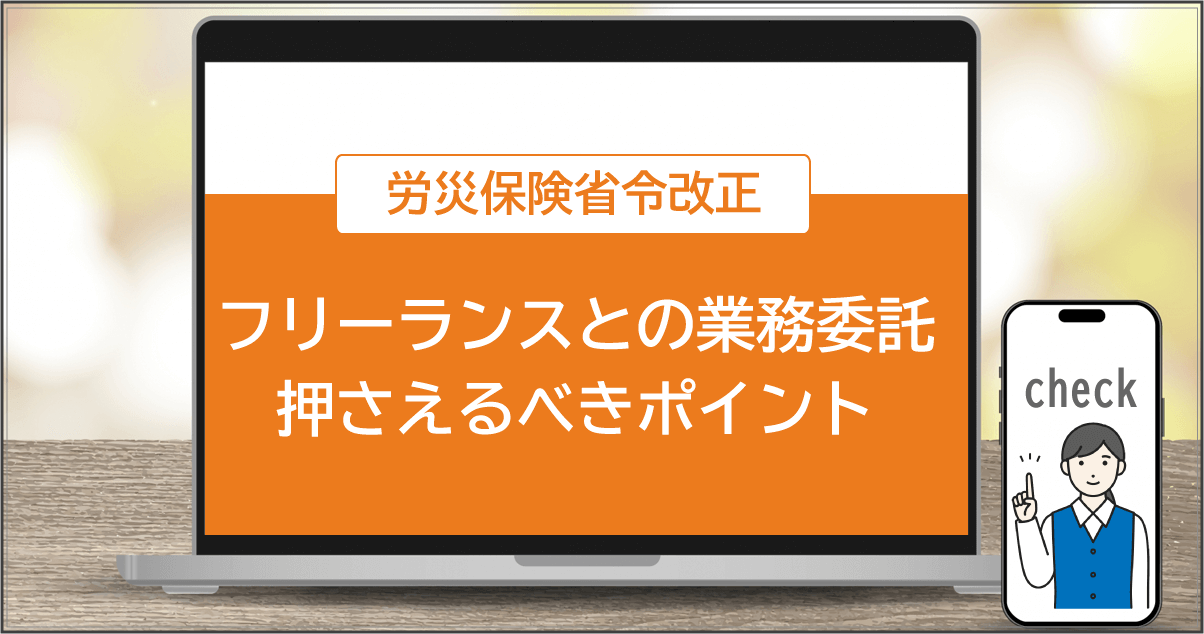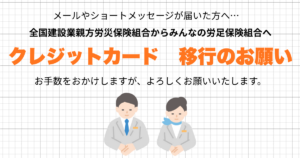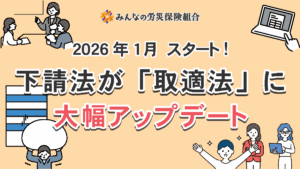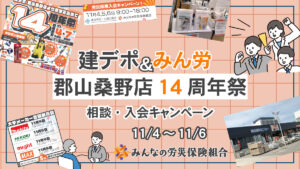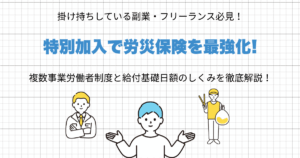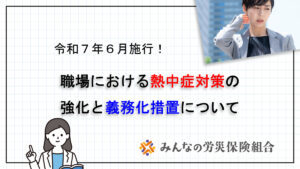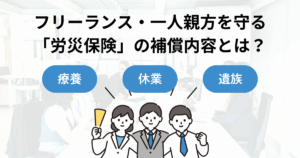特別加入制度の拡大に伴う請負元・請負先の注意事項を徹底解説
令和6年11月から適用範囲が広がった「特別加入制度」。フリーランスの働き方が増える一方で、企業(請負元)の側でも労働者性の認定や安全配慮義務などのリスクが注目されています。実際に業務を委託する・受託する立場それぞれで、具体的にどのような点に配慮すべきなのでしょうか。
拡大される特別加入制度の概要とともに、請負元・請負先双方が心得ておくべき注意事項を総合的に整理していきます。
【この記事でわかること】
- 令和6年11月の省令改正で特別加入が広がる背景
- フリーランスが特別加入できる仕組みとメリット
- 請負元(発注者)が注意すべき法的リスクと実務上のポイント
- 請負先(フリーランス)が確認すべきこと、労災保険への加入方法

お手軽に、PC/スマホで完結!
保険番号も最短当日発行されます!
令和6年11月から変わる「特別加入制度」とは
近年、フリーランスや一人親方として働く方が増える一方で、「万が一のケガや病気に備えがない」という不安が指摘されてきました。そうした実情を踏まえ、令和6年11月の省令改正では、労災保険の特別加入制度が大幅に拡充されることが決定。従来は加入できなかった業種・業務のフリーランスでも、公的な労災補償を受けられる可能性が広がります。
この特別加入制度がどう変わるのか、どんな人が対象になるのかを中心に、その背景と概要をわかりやすく解説します。
特別加入制度の拡大背景
従来、労災保険は「雇用される労働者」が対象でした。しかし近年、フリーランスや個人事業主といった働き方が急増し、実質的に労働者と変わらない業務形態にもかかわらず補償が受けられないケースが問題視されるようになりました。そこで国は、特別加入という形で、一人親方や個人タクシーなど一部の自営業者に限って労災保険加入を認める仕組みを整備してきました。
令和6年11月の省令改正では、この特別加入制度がさらに拡大され、「特定フリーランス事業」として、多くのフリーランスが労災保険に入りやすくなります。これにより、業務中のケガや病気で長期の休業が必要になっても、国の補償を受けられる可能性が高まるのです。
フリーランス(請負先)のメリットと注意点
特別加入制度の拡大によって、フリーランスが公的保険の補償を受けられる範囲は大きく広がりました。実際に業務中のケガや病気は、収入の途絶や高額な治療費など、フリーランスにとって深刻なリスクとなります。そこで頼りになるのが、労災保険の「特別加入」です。
一方で、特別加入にかかる保険料は自己負担であり、加入時の手続きや保険料設定などいくつか注意点も存在します。以下では、フリーランス(請負先)の立場から見たメリットと気をつけたいポイントを整理していきましょう。
フリーランスにとっての特別加入のメリット
- 公的補償による安心感
仕事中や移動中(通勤災害含む)のケガや事故が起きた場合、治療費や休業中の補償を国が行ってくれるため、自己負担が大幅に軽減されます。 - 取引の信用力アップ
請負元(発注者)から見ると、業務リスクを自力でカバーできるフリーランスは安心して業務を任せやすい存在です。特別加入しているかどうかが契約条件になるケースも増えています。 - 自分自身だけでなく、家族を守るためにも重要
フリーランスは雇用保険や健康保険や厚生年金など、会社員のような仕組みがない分、自分のことや家族などに対しての経済的な部分においても自己責任で守らなければなりません。公的制度の活用によって、万が一の事態から家族や生活を守ることにもつながります。
フリーランスとして特別加入する際の注意点
- 保険料は自己負担
会社員のように企業が保険料を負担してくれるわけではなく、自分で保険料を支払う必要があります。 - 賃金日額の設定がカギ
補償額を大きくすれば保険料は上がり、低く設定しすぎれば万一のときに十分な補償が受けられません。 - 対象業務かどうかの確認
新たな省令改正で対象拡大とはいえ、すべてのフリーランスが無条件で加入できるわけではありません。自分の業種・業務が適用範囲に入っているか確認する必要があります。

お手軽に、PC/スマホで完結!
保険番号も最短当日発行されます!
請負元(発注者)が注意すべきポイント
フリーランスへの業務委託が増える一方で、令和6年11月の省令改正による特別加入の拡大は、発注者側にも新たな責任やリスクマネジメントを求めることになります。形式上は請負契約であっても、実質的に労働者とみなされるケースや、安全配慮義務が問われる事態も考えられます。
ここでは、請負元(発注者)の立場から具体的にどのような点に気をつければよいのか、重要なポイントを整理していきましょう。
安全配慮義務と損害賠償リスク
- 「実質的な労働者性」があると認定されるリスク
形式上は業務委託契約でも、実態として発注者がフリーランスを厳しく指揮監督している場合、労働者として認定される可能性があります。
その場合、フリーランスとしての労働性ではなく、労働者性があるとし、企業は労働法上の安全配慮義務を負い、万一事故が起きた際に損害賠償を請求されるリスクがあります。 - ハラスメント・安全管理にも配慮が必要
フリーランスへの言動や作業環境に対しては、労働者とは別の立場でも一定の安全・衛生管理措置が求められる流れになっています。
現場での安全指導やハラスメント防止策などを怠ると、結果的に企業の責任が問われるケースもあり得ます。 - フリーランス新法など関連法令の整備
フリーランスとの取引を公正に行うための「フリーランス新法」正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」やガイドラインが続々と整備されており、発注者の説明責任や契約書での明記事項が厳格化する方向です。
最新版の法令や通達をこまめにチェックしましょう。
労災保険の加入確認とそのメリット
- 請負元としてフリーランスに特別加入を促すメリット
業務中の事故が起きた際、フリーランスが労災特別加入していれば、公的保険で補償されるため、企業が独自に補償する負担が軽減されます。 - 加入証明書で加入状況を確実に把握
「労働保険番号」や「特別加入証明書」などの写しを契約前に提示してもらうことで、実際に加入しているかどうかを確認できます。口頭だけではトラブルになりかねないため、必ず書面(またはPDF等)の形で確認すると安心です。 - 契約書への記載事項
- 非雇用関係の明確化:あくまで委託契約であり、労働契約ではないことを記す。(業務委託契約書など)
- 特別加入の有無:フリーランスが特別加入しているかどうかを明示的に書き込むか、加入を条件にするなどの対応を検討。
- 自己安全管理の条項:フリーランスにも安全管理の責任がある一方、発注側の安全配慮義務も完全には消えないため、双方の範囲を明確化する。
現場での安全管理:発注者とフリーランスの協力が不可欠
実際の作業現場においては、労務管理上の契約形態に関わらず事故や災害リスクがつきまといます。フリーランスだからといって、一方的に自己責任を押し付けるのではなく、発注者が安全情報を適切に提供し、フリーランス自身も現場ルールを遵守することが重要となります。
ここでは、相互の協力体制を整えるうえで押さえておきたい具体的なポイントを確認していきましょう。
- 過度な指示・監督は避けつつ、必要な安全情報は共有
発注者が業務の進め方を細かく指示しすぎると、労働者性を推認されるリスクが高まります。ただし、作業現場の危険情報を十分に共有し、安全防護具の着用を促すなど必要な安全指導はしっかり行うべきです。 - 災害発生時の連絡フローを明確化
もしケガや事故が起きたときに連絡をどのように行い、どんな手続きが必要かをあらかじめ決めておくと、迅速に対応できます。 - 一人親方やフリーランスも安衛法上の保護が進む方向
一人親方などは従来から安全衛生法の対象外とされる部分がありましたが、法改正によって労働者同等の安全対策を求められるケースが増えています。企業としてはフリーランスも安全管理の対象と捉え、社内ルールを見直す必要があります。
まとめ
特別加入制度が拡大されることで、フリーランスは従来よりも公的補償を受けやすくなり、仕事の安定性や取引先からの信頼性が高まります。一方で、発注者も、安全配慮義務や労働者性のリスクを軽減できる可能性があり、スムーズな契約関係を築きやすくなるでしょう。
ここでは、令和6年11月以降における特別加入制度のメリットを改めて整理し、双方が活用する際に覚えておきたいポイントをまとめてみます。
令和6年11月以降の特別加入拡大で双方が得られるメリット
- フリーランス(請負先)
- 公的保険による手厚い補償
- 取引先からの信用度アップ
- 自己責任リスクの大幅軽減
- 請負元(発注者)
- 補償トラブルのリスク低減
- 労働者性の認定リスクを回避しやすい
- 安全・衛生対策を講じることで企業イメージ向上
令和6年11月から省令改正された特別加入制度の拡充によって、フリーランスとして業務を受託する方々が労災保険に加入しやすくなります。一方、請負元(発注者)は「安全配慮義務」「フリーランス新法」などさまざまな面で対応を求められ、今後はよりいっそう契約・安全管理面を整備する必要があります。
補足
フリーランスとの取引に関する制度整備が進む中、厚生労働省や国土交通省からもガイドライン等が示されています。厚労省の「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」では、フリーランスが労働者に該当する場合の判断基準や、発注者が遵守すべき事項が整理されています。
また、厚労省は「個人事業者等の安全衛生対策について」の中で、一人親方・フリーランスに対する安全衛生水準の向上に努めるよう呼びかけています。具体的には、デリバリーサービス等の業種別対策の推進や、業界団体を通じた自主的な安全衛生活動の支援などが挙げられています。
国土交通省も、自ら所管する業界(建設業や運送業等)に対しフリーランス新法の周知徹底を依頼しており、安全配慮を含め適正な取引慣行の確立を促進しています。
建設業においては従前より一人親方問題が指摘されてきた経緯もあり、「建設現場の一人親方であっても安全配慮義務が発注者に課される」との見解も示されています。
今後、労働安全衛生法そのものの改正によって、フリーランスも労働者同等に保護する規定が整備される見通しです。
現行制度下でもフリーランスへの特別加入適用やハラスメント防止義務化など大きな変化が生じています。発注者は最新の法令・ガイドラインを常に確認し、自社のフリーランス活用の実態を見直して、安全管理・契約内容をアップデートすることが肝要です。
以上のポイントを踏まえ、実務担当者はフリーランスとの安全で公正な取引環境づくりに努めていきましょう。特別加入制度の積極的な活用確認、安全配慮義務の履行、適正な契約書整備、現場での安全管理など、これらを徹底することで、フリーランスにも安心して働いてもらえ、発注者自身も法的リスクを軽減することができます
労働力の多様化が進む中、企業のコンプライアンス姿勢が問われています。最新ガイドライン等を参考に、適切な対応を講じましょう。
参考リンク・お問い合わせ先
- 厚生労働省:特別加入制度に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/(特別加入に関する最新情報を随時更新) - 労働保険事務組合や業界団体
特別加入が認められた各種団体の情報を確認し、自身の業種に合うところへ問い合わせを行いましょう。