特別加入制度とは、読んで字のごとくですが「特別に加入できるようにした制度」のことです。
労災保険という呼び方か自体も略称で、正式名称は「労働者災害補償保険」と言います。
保険制度内容は、労働者が労働災害(以下、業務災害)に遭われた時、政府が経済的補償をする保険制度です。
フリーランスも一人親方も、自営業者や個人事業主も「労働しているから労働者じゃないの?」「なんで特別なの?」と思われるかもしれません。
実は労働基準法第9条で定められており「企業に雇用され労働対価として賃金を得ている方」を労働者として表しています。反対に、労働者に含まれない方は、以下の3つの働き方をしている方です。
- 事業主(フリーランス・一人親方・個人・法人)
- 法人役員(役員報酬を得ている方で、賃金の役員は含まれない)
- 事業主の親族
実態としてですが、フリーランスも一人親方も、自営業者や個人事業主も、仕事=労働をしなければ、その対価としてお金はもらえませんし、お金がなかったら資本主義の下では生活をすることもほとんどできません。
ですから、「労働者ではないけれど、労働者と同じような働き方はしているよね。特別に労災保険(労働者災害補償保険)へ加入できるように制度を整えましょう」ということで法律が制定され、フリーランスや一人親方、自営業者の方たちの行っている事業によって加入できるようにししたのが特別加入制度の労災保険です。
ですから名称に「特別」がついています。
行っている事業によって加入とは?
特別加入制度は、フリーランスや一人親方、自営業者や個人事業主のための労災保険への加入制度ということはご理解いただけたと思います。
では、行っている事業によって加入できるようにしたとはどういう意味でしょう。
皆さんが行っている仕事(事業)は、おのおの違いがあることは言うまでもありません。
特別加入制度労災保険は、行っている仕事内容によってにカテゴリーを別け、行っている事業ごとに労災保険加入ができるようになっています。
どの団体や組合が「何の事業をしている方の加入受付」をできるのかが重要です。
一つの団体がすべての事業の受付を執り行うことがでると勘違いされている方もいらっしゃいますが、事業を別けていますので、どの団体が何の事業(業務・業種)に対応しているのか必ず確認しましょう。
では、どれだけの事業(仕事内容や業務)に別けられているかを見ていきましょう。
特別加入制度者の範囲(事業)
第1種:中小事業主等の特別加入
労働者を使用する中小事業主とその家族従事者などが対象で、労災保険へ加入することができます。
労働者の目安としては、4時間以上/日若しくは、20時間以上/週、87時間以上/月、100日以上/年、時間的拘束を受けて労働し、対価として賃金を得ているものですが、事業主に雇用され、労働契約に基づいて労働を提供し、賃金を受け取る方が労働者となります。
間違えやすいのが、家族専従者と青色専従者です。事業主の家族で、事業に従事している人は同じ要件ですが、家族従事者は扶養控除の対象になるが、給与は経費として認められず反対に、青色専従者は、扶養控除対象から外れ、給与支払いは経費として認められます。ただし、青色専従者は、青色申告をすることが大前提になります。
第2種:一人親方その他の自営業者の特別加入
特1:自動車及び原動機付自転車、自転車を使用しての貨物運送事業
自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車、若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)のとで、雇用されずに自ら行っている方のための労災保険です。
特2:建設事業
土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは、解体又はその準備の事業(大工、左官、とび職人など)です。一人親方という名称は、建設業界でよく使われており、その方たちのための労災保険で有名になりました。また、原状回復には東日本大震災のちに付加された「除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などの原状回復」の事業を行う方も含みます。
特3:漁船による水産動植物の採捕の事業
漁船で漁を行い(水産動植物の採捕をする方)生活を営む方用の労災保険です。船員法第1条に規定する船員が行う事業と遊漁船(釣り船等)は対象ではありません。
特4:林業の事業
森林を管理し育て、木材を生産する仕事を行う方のための労災保険です。
特5: 医薬品の配置販売事業
医薬品医療機器等法第30条(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の製造販売)の許可を受けて行う医薬品の配置販売業を雇用されずに行っている方の労災保険です。
特6:再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
再生資源取扱いの事業と呼ばれ、廃棄物や不要になったものを回収・加工し、再び資源として利用できるようにする事業を、企業請負の元行っている方用の労災保険です。建築現場での解体に関しては、特2で取り扱われます。
特7:船員法第1条に規定する船員が行う事業
船舶の運航や操業に関連する事業のことで、貨物輸送・旅客輸送 ・海洋調査・海洋開発で等で、企業などの請負で事業を行う方用の労災保険ですが、漁業に関しては、特3で取り扱われます。
特8:柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業
国家資格を得て、脱臼・骨折・打撲・捻挫などの外傷に対し、整復・固定・マッサージ・電気療法を用いて施術を行う方用の労災保険す。ただし、柔道整復師免許は医師免許とは違いますので、医療的行為はできません。
特9:改正高年齢者雇用安定法第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業
企業が70歳までの高年齢者の就業機会を確保するための措置の一つで、創業に関する支援と事業主が実施する社会貢献事業等への従事支援のことです。企業が雇用することではなく「支援」することが重要な点で、支援される方が労災保険への特別加入をすることが可能です。
特10:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業
通称「あはき法」と呼ばれ、それぞれの業務や資格について定められており、その業務範囲内で業務を執り行う方が加入できる労災保険です。
特11:歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業
特定の人に対する歯科医療に利用される、補綴物、充填物、矯正装置を作成、修理、または加工する業務です。歯科医師の指示に基づき、患者さんの歯の修復や矯正に「必要な装置を専門的に製作」する業務を行います。医師や企業に雇用されず、請負のもと自ら業務を行う方のための労災保険です。
特12:特定フリーランス事業(令和6年11月新設)
フリーランスが企業や依頼主から業務委託を受け事業をを行う方や、消費者本人から委託を受け、事業を行う方で、今まで労災保険へ加入できなかった方が対象となります。
ただし、大前提としてまず企業から業務委託を受けている事業が主としてあり、その事業を消費者からも受けるという図式になります。消費者からのみ事業を受けるフリーランスや、企業から受けている事業と違う事業を消費者から受ける場合は、労災保険の対象外となりますのでお気をつけください。
第2種:特定の作業に従事する人の特別加入
(1)特定農作業従事者
(2)指定農業機械作業従事者
(2)国又は地方公共団体が実施する訓練従事者
(3)家内労働者及びその補助者
(4)労働組合等の常勤役員
(5)介護作業従事者及び家事支援事業者
(6)芸能関係作業従事者
(7)アニメーション制作作業従事者
(8)ITフリーランス
※ここでの詳しい説明は、厚生労働省の特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)の「特別加入者の範囲」をご案内します。
厚生労働省の特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)の「特別加入者の範囲」
第3種:海外派遣者の特別加入
独立行政法人国際協力機構等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除きます。)を行う団体から派遣され、開発途上地域で行われている事業に従事する方並びに、国内で行われる事業(有期事業を除きます。)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者です。
海外にある業務として、「保険業・金融業・不動産業・小売業においては50人」「卸売業・サービス業においては100人」「それ以外の業種においては300人」以下の常時雇用人数がいる事業主、及びその他労働者以外の方が加入できる労災保険です。
補償はどこで誰がどのように出してくれるのか
保険の契約において必ず覚えておいてほしいものに、「保険者と被保険者」という言葉と関係性です。
保険者(ホケンジャ)とは、その保険事業の運営主体のことを表し、被保険者(ヒホケンジャ)は、その保険へ加入し、補償を受ける側の人を表します。
特別加入制度の労災保険では
保険者は、政府における行政機構の「厚生労働省」ですので、簡潔に表せば政府が補償してくれるということになります。
被保険者は、特別加入制度の労災保険へ加入し補償を受ける側ですから、ここでは「フリーランス・一人親方・個人事業主などの本人」となります。
では、どのように補償を出してくれるかですが、業務災害が起きた際には以下の流れになります。
業務災害が発生し、病院で治療を受けるときには速やかに加入手続きをした特別加入承認団体
へ報告する(方法は各団体によって違います)
労災事故報告を受け、特別加入承認団体が業務災害時の補償給付用各種書類を作成(各団体によって無料・有料・外部委託とあります)
特別加入承認団体が作成した業務災害時の補償給付用各種書類がお手元に届きます。名前や生年月日、記載されている日付けなど確認します
各種書類を治療を受けている病院へ提出します。
治療を受けている病院の医師が、書類に相違ないという意味でサインをします。
医師がサインした書類を誰がどこに提出するかですが、病院によって違うようです。
病院がそのまま管轄の労働基準監督署へ提出してくれるところもあれば、患者本人へ書類を戻し、患者本人が管轄の労働基準監督署へ送るということもあります。団体によっても違いがありますので、確認しておきましょう。
労働基準監督署が書類をもと労災発生要因を調査し、問題がなければ労働局へ書類が回ります。その書類を受けて補償給付が決定し、被保険者への補償が開始されます。
このように書類によってすべてが決まりますので、労災事故が発生しましたら早急に対応していきましょう。
労災保険の補償給付内容は、別のブログでご紹介します。
民間の保険会社と何が違うの?
この特別加入の労災保険は、政府が保険者であることはご理解いただいたかと思います。
政府が事業運営主体、つまり公的機関が行っている事業のことを「公営」と言いますので、この保険のことを「公営保険」と表します。
反対に、民間が事業運営主体となっている保険のことは、「民営保険」と表します。
公営保険の例
- 労災保険制度(特別加入労災保険含む)
- 雇用保険制度
- 医療保険制度(国民健康保険・職域国民健康保険組合など)
- 年金保険制度(厚生年金保険・国民年金保険など)
- 介護保険制度
民営保険の例
- 生命保険(終身保険・定期保険・逓増定期保険など)
- 医療保険(終身保険・定期保険など)
- 特定疾病保険(がん保険・三大疾病保険・介護保険など)
- 年金保険(年金積立保険など)
公営保険は政府が保険者で、補償給付は政府行政機構(厚生労働省など)が行うもの
民営保険は民間保険会社が保険者で、補償給付は民間企業(株式会社○○生命など)が行うもの
以上のように覚えておけば間違いないでしょう。
特別加入の労災保険は承認団体からのみ加入手続きができます
特別加入制度の労災保険への加入の手続きは、お住まいの市町村区を管轄する「労働基準監督署」では手続きができません。
あくまで、厚生労働省・労働局が「承認」をした団体(特別加入承認団体)からのみ受付が可能です。
お問い合わせであるのが、労働基準監督署へ行ったが対応してくれなかったという内容です。
対応してくれないのではなく、対応することができないというのが正しいでしょう。
どの団体がどこにあるかというのは、お住まいを管轄する労働基準監督署もしくは、各都道府県にある労働局のホームページをご覧ください。
どの団体が、なんの事業(業種・業務)に対応しているか、詳しく記載されています。
どこの特別加入承認団体が良いのかわからない
特別加入承認団体は、確かに公営保険の窓口であることには間違いありませんが、その公営事業における運営方法などに関し、政府からの補助も補償も一切されていません。
いうなれば、運営が困難になっても政府から助けてもらえるはずもなく、民間企業と同じく倒産(解散)する可能性もあります。
ですから、特別加入承認団体(組合など)によって、サービス内容も取り扱い金額もすべて違うといっても過言ではありません。
どの団体から加入すれば、安いところはどこか、サービスはどうなっているかなどは。ご自分で調べるしか方法がありません。
ご加入手続きをするときは安さのみ求めるのではなく、サービス内容をよくご確認の上、自分にあった団体(組合など)から手続きするようにしましょう。
まとめ
令和6年11月度に法制定された「特定フリーランス事業」を行う方も、労災保険への加入(特別加入制度の労災保険)ができるようになったことは、いままで政府に守られることがなかった「フリーランス」の方も補償給付を受けられるという大変重要な法制定となっています。
これを機会に、フリーランスや一人親方や個人事業主の方も、労働を起因としたケガに対応できますので、今一度ご検討いただきますようお願いいたします。
※請負元様においては、フリーランスや一人親方・個人事業主を元請先として業務委託する際において、令和6年4月に改正された「労働安全衛生法」令和6年4月に改正された「安全配慮義務」並びに、令和6年11月に制定された「フリーランス法」をご理解いただき、請負法のもと「業務委託契約」を交わし、特別加入制度の労災保険への加入の確認、並びに加入促進をお願いいたします。
みんなの労災保険組合(通称:みん労)は、厚生労働省労働局、労働基準監督署の承認を正式に受け活動します。
ホームページに記載された料金以外は一切いただくことはありませんのでご安心ください。
組合員様には、労災保険にかかわるすべての申請書類作成を無料で代行します。
ご加入いただいた組合員様は、安心してお仕事ができます。
みんなの労災保険組合は、労災保険への加入から脱退、業務災害の報告があった時は即座に対応いたします。
労災保険の専門家がスピーディーに、しかも丁寧にあなたをサポートします。
万が一に備え、みんなの労災保険組合で安心安全な労災保険サポートを受けましょう




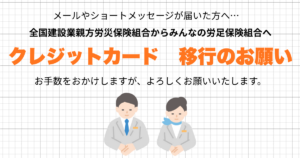
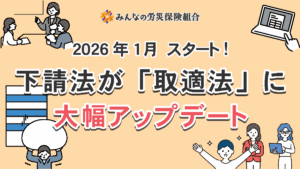
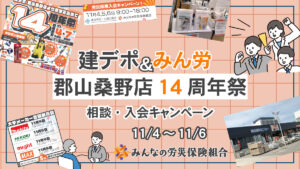


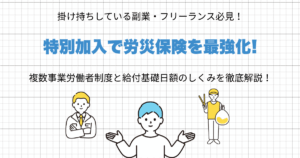
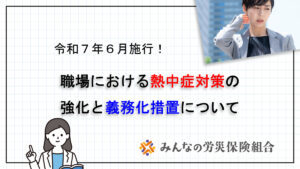
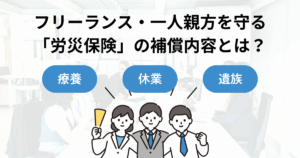
コメント
コメント一覧 (3件)
[…] 特別加入制度の労災保険とは? […]
[…] 特別加入制度の労災保険とは? […]
[…] 特別加入労災保険対象者 […]